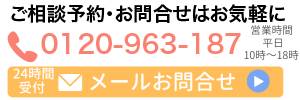相続税の基本
Q: 相続税はいつ、誰に、どのくらいかかるのですか?
A: 相続税は亡くなってから10か月以内に申告・納税が必要です。
相続税は、相続財産があるからといって必ずかかる税金ではなく、一定の金額を相続しなければ発生しません。日本人の約1割程度しかかからないと言われています。
相続税が発生する場合は、亡くなった日から10か月以内に申告・納税をしなければなりません。相続税の申告は、申告書を提出するとともに税金も納めなければならず、申告期限までに納税できない場合には延納や物納の手続きも併せて行う必要があります。
不動産と相続税
Q: 不動産を相続した場合、税金はどのように計算されますか?
A: 相続した不動産は相続税評価額で計算され、登録免許税も必要です。
不動産の相続では、まず相続税の計算のために相続税評価額が用いられます。土地は路線価等を基に計算し、建物は固定資産税評価額が基準となります。これらは一般的な市場価格より低く評価される傾向があります。
また、不動産の名義変更(相続登記)の際には、登録免許税として「不動産の評価額×0.04」の税金を納める必要があります。例えば固定資産評価額が1,000万円の不動産なら、40万円が国に納める税金になります。
相続した不動産の売却と税金
Q: 相続した不動産を売却する場合、税金はどうなりますか?
A: 売却益に対して譲渡所得税がかかる場合があります。
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。計算式は: 売却価格-取得価格-譲渡費用-特別控除=課税対象の譲渡所得
取得費が不明な場合は売却価格の5%と見なされるため、売買契約書等は必ず保管しておくことが重要です。税率は所有期間によって異なり、5年超の長期保有は約20%、5年以下の短期保有は約40%となります。
Q: 実家や空き家を売却する際に税金を安くする方法はありますか?
A: 「空き家特例」や「居住用財産の特例」を利用できる場合があります。
空き家特例(空き家の譲渡所得3000万円特別控除)
相続した空き家を売却する際、以下の条件を満たせば譲渡所得から3000万円を控除できます:
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
- 戸建てであること(分譲マンションは対象外)
- 相続開始直前まで被相続人が1人暮らしをしていたこと
- 相続時から譲渡時まで事業用・貸付用・居住用に使用されていないこと
- 1億円以下で売却されること
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
居住用財産の3000万円特別控除
自分が住んでいる不動産(マイホーム)を売却する場合、譲渡所得から3000万円を控除できます。主な要件は:
- 自分が住んでいる物件の売却であること
- 以前にこの特例や他の譲渡所得の特例を受けていないこと
- 売主と買主が特別な関係(親子・夫婦など)にないこと
- 確定申告をすること
ただし、相続後その物件に住んでいない人が売却する場合は使えません。また、住宅ローン控除との併用はできないため、どちらが有利か計算する必要があります。
遺産分割と相続税
Q: 遺産分割が長引いた場合、相続税はどうなりますか?
A: 法定相続分で一旦納税し、分割後に更正の請求を行います。
相続税の申告期限(10か月)内に遺産分割が決まらない場合、一旦「法定相続分」で相続したものとして相続税を納税します。この場合、各種特例は使えないため税額が高くなる場合があります。
遺産分割が決まった後、更正の請求を行うことで差額は還付されますが、一旦高額な相続税を納税する必要がある点と、手続きが二度手間になる点に注意が必要です。
相続税の申告・納税
Q: 準確定申告とは何ですか?
A: 被相続人の1月1日から亡くなるまでの所得を計算して申告・納税する手続きです。
年の途中で亡くなった方がいる場合、その年の1月1日から亡くなるまでの所得を計算して申告・納税する「準確定申告」が必要です。これは相続税とは別の手続きで、相続人が行います。
ただし、相続放棄を検討している場合は、準確定申告の手続きはしてはいけません。準確定申告は相続人が行う手続きであり、相続を認めたこと(単純承認)となるためです。相続放棄をした相続人は準確定申告をする必要はありません。
相続対策と税金
Q: 相続税を安くするための対策はありますか?
A: 生前贈与、不動産活用、相続税評価の低い資産への移行などがあります。
相続税対策の基本は、生前に計画的に資産を減らすか、相続税評価額の低い資産に移行することです。主な方法として:
- 年間110万円までの基礎控除を利用した生前贈与
- 教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与特例の活用
- 不動産の有効活用(賃貸アパート経営など事業用資産への転換)
- 相続税の評価が低い資産への移行
- 生命保険や死亡退職金の活用
ただし、相続対策は専門的な知識が必要な場合が多いため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。